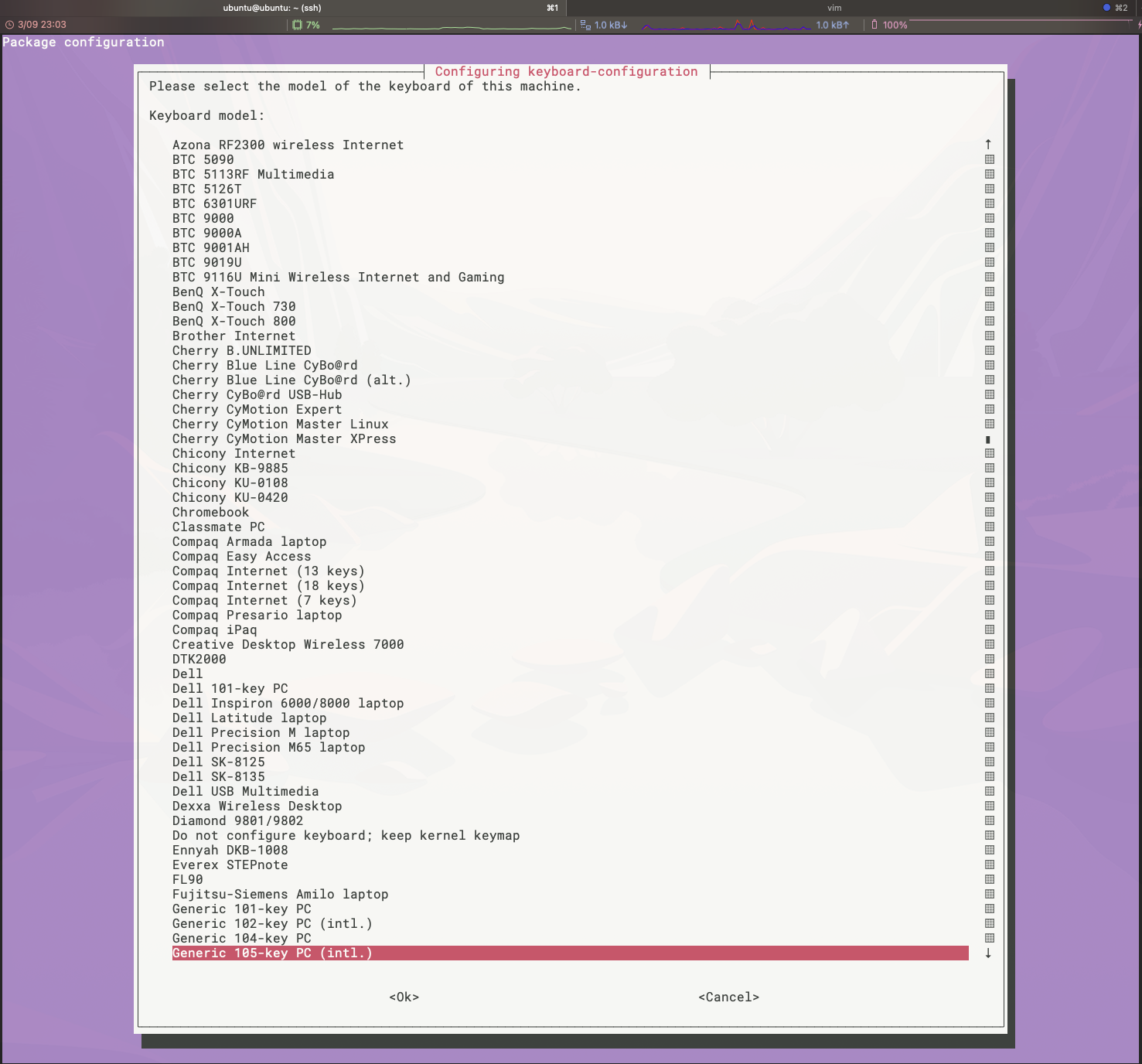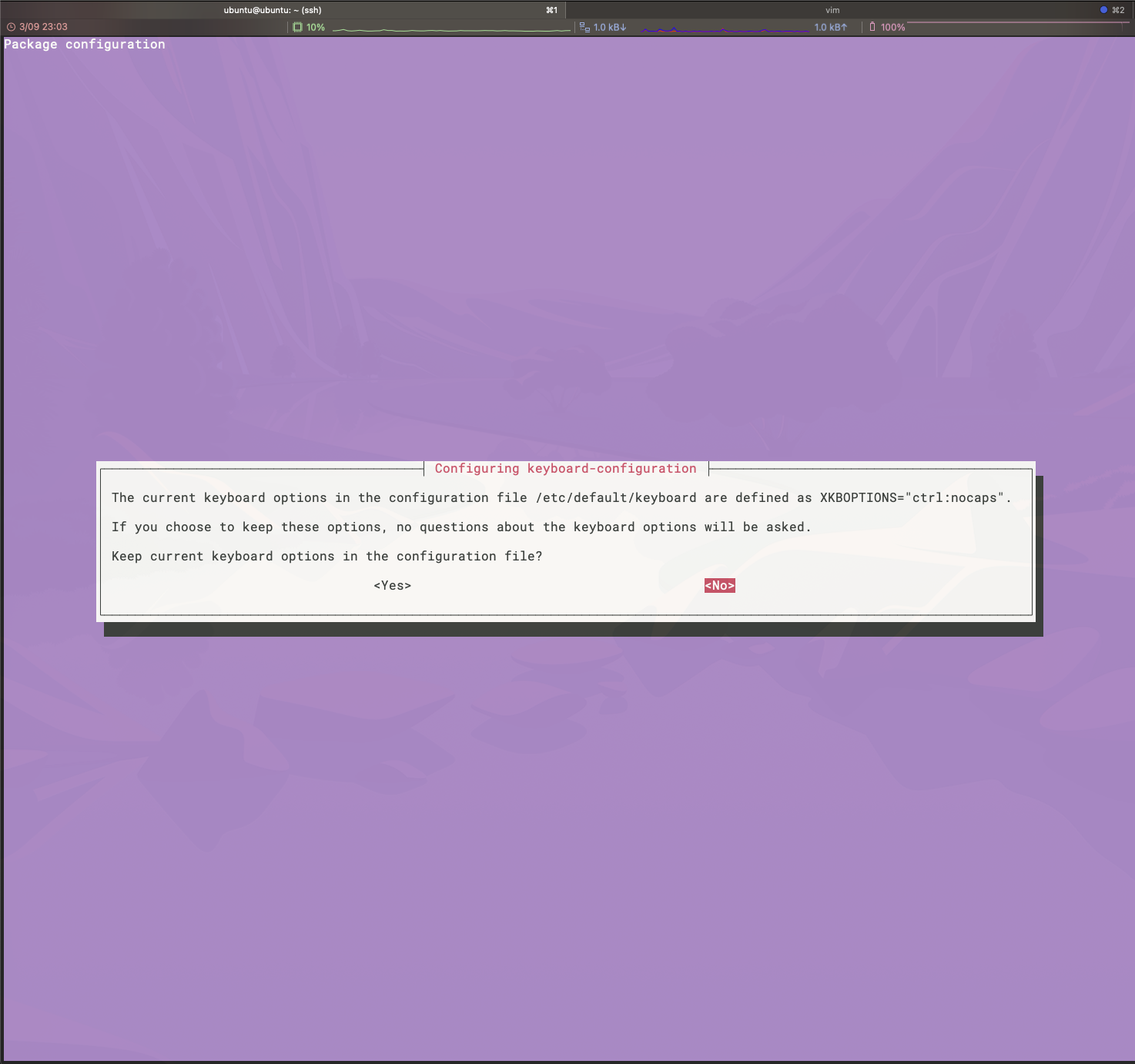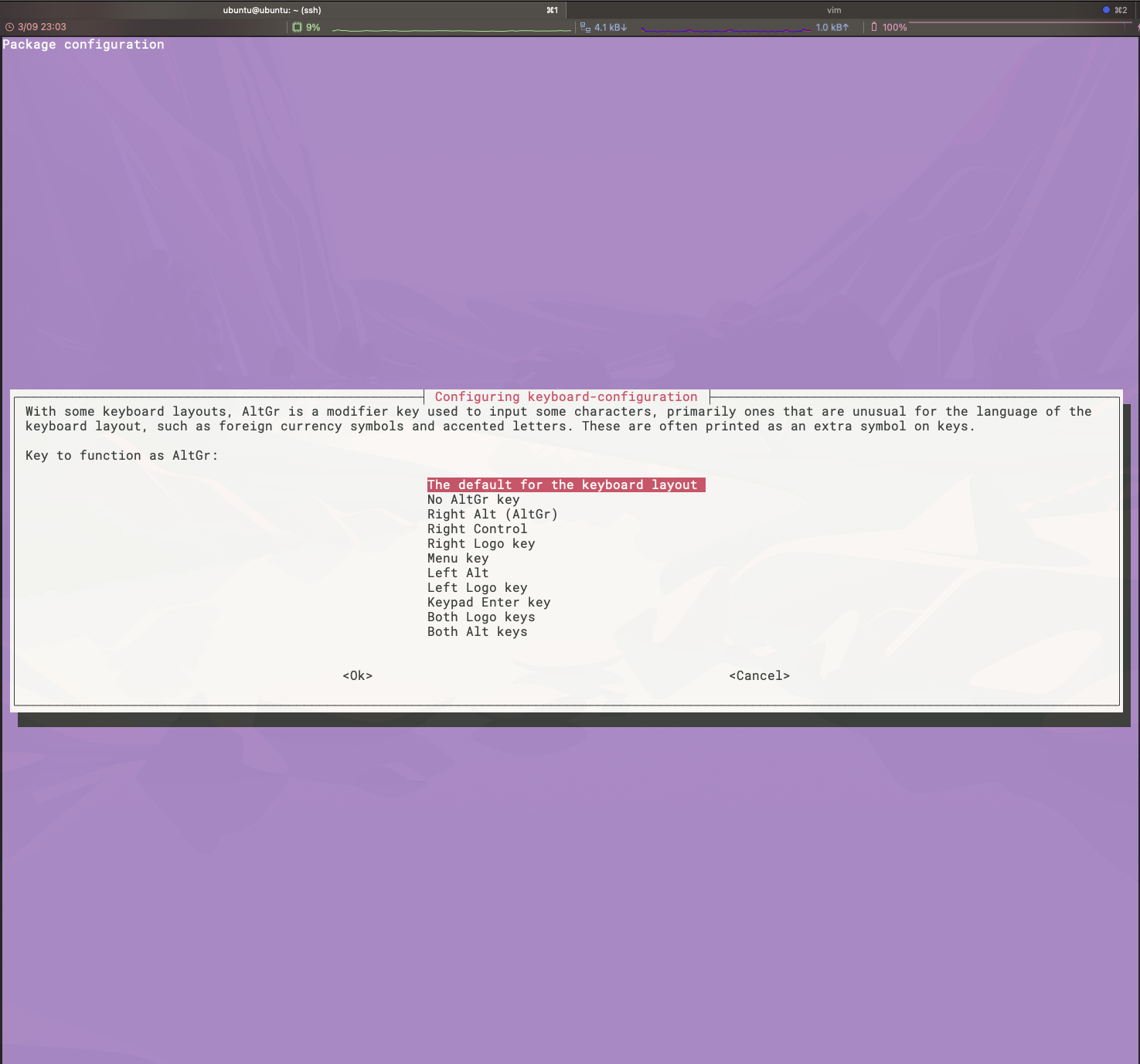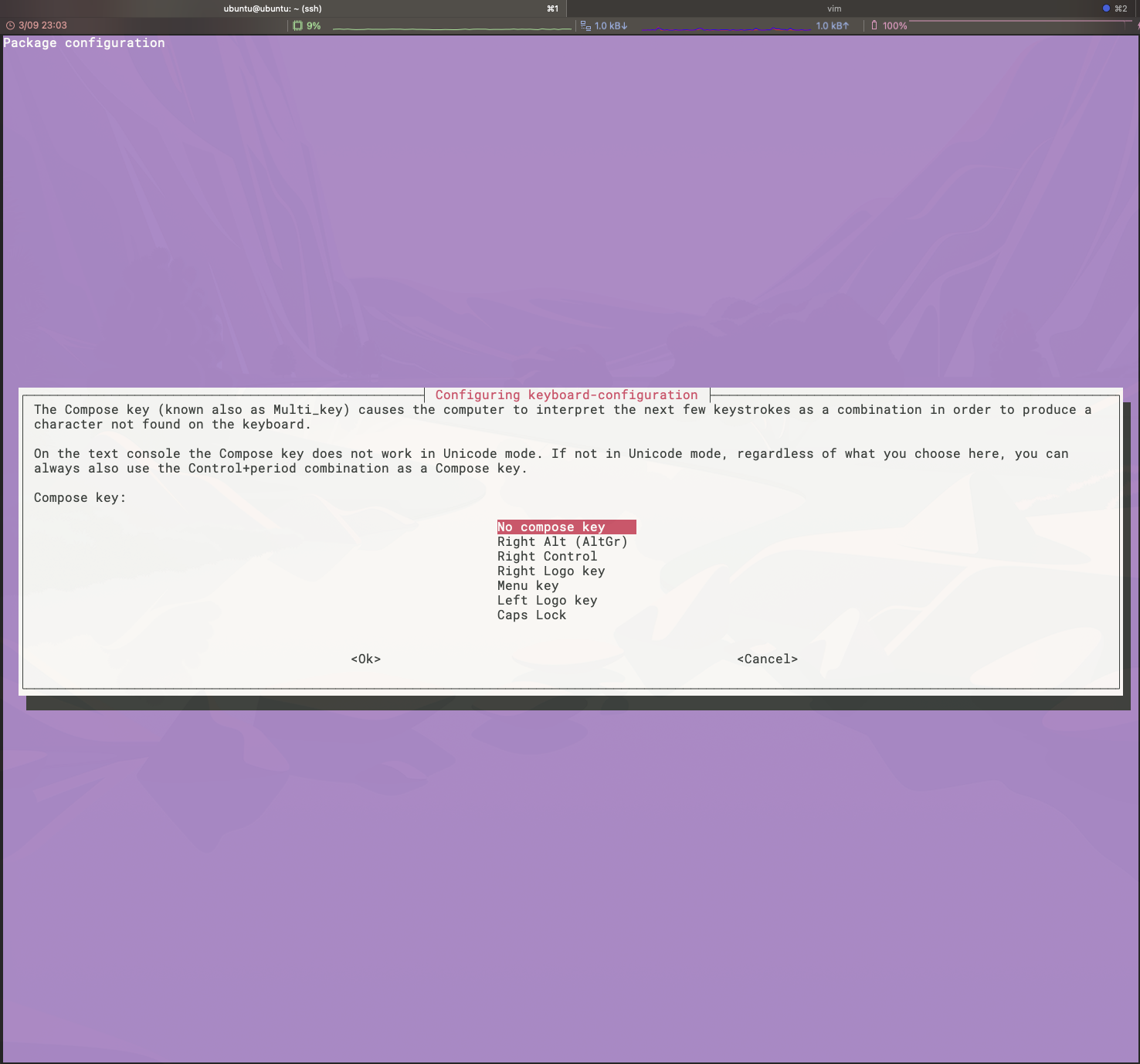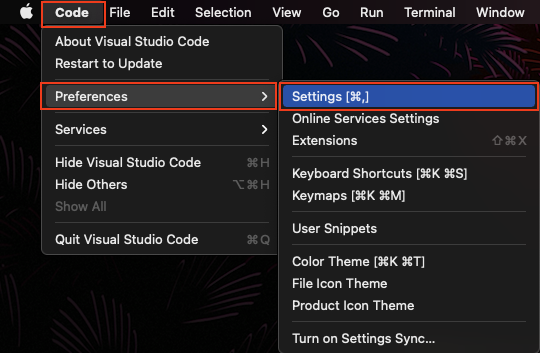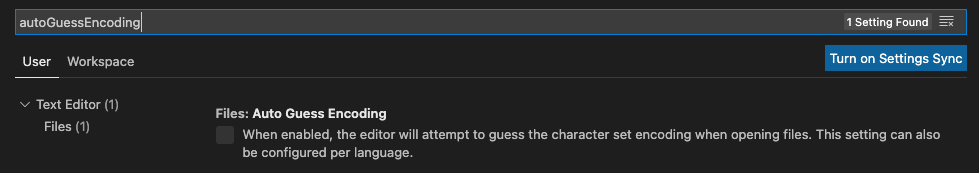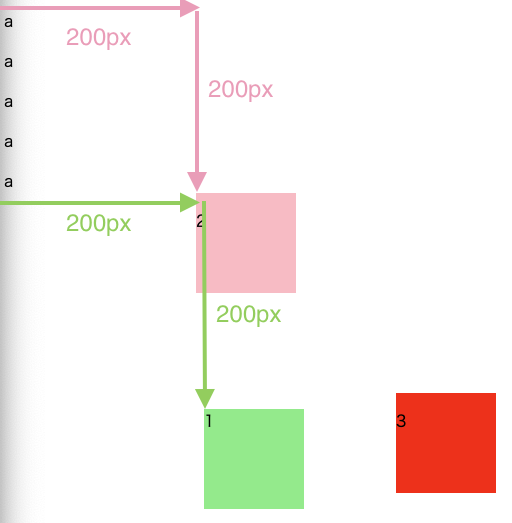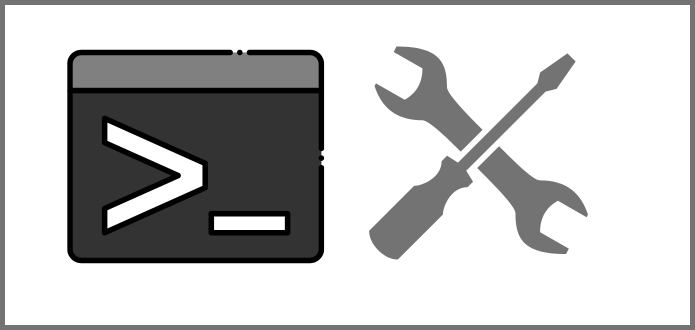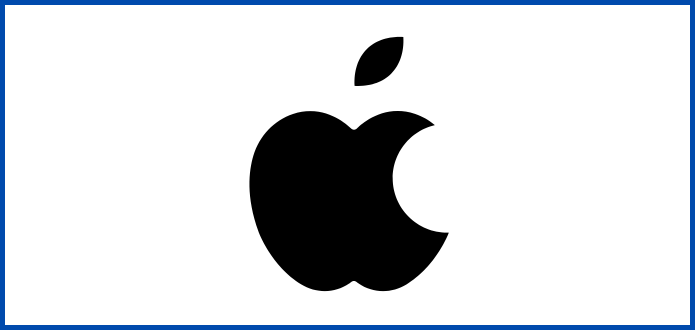タグはなんのためにあるのか
コミットを指定するためにSHA 1IDを使用するが、毎回選択するのは面倒くさいし間違える可能性があるので、よく使う可能性のあるコミットに命名することで、いちいちSHA 1IDを指定しなくてよくできる
コミットにタグを追加する
タグをつける
1 | |
タグをつけるときは、-mスイッチを使用すればメッセージをつけることもできる
1 | |
タグを消去する
1 | |
これが表示されれば成功1
Deleted tag 'タグ名' (was SHA1)
タグの一覧を表示する
1 | |